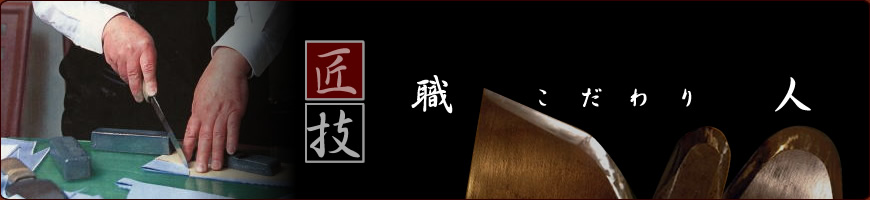醤油や味噌といった日常品は、なるべく廉価なもので済ますという考え方がある。しかし毎日のものだからこそ、よいものを使うという人もいる。理は双方にあるのだろうが、当然、出来上がった料理のおいしさには相応の差が出る。料理に対する考え方や情熱などにも歴然とした隔たりがあり、味わいの品格や深みがまるで違ってくるのだ。
シャツも同じである。男性なら数枚は持っている。ビジネスマンなら毎日着用する必須アイテムだ。シャツを単に背広のインナーととらえる場合は廉価品を着る。だが既製品ゆえに体にフィットするとは限らない。ときには人問のほうがシャツに合わせることになる。袖が長い場合には銀色のアームリングなどをして調節したりする。廉価な調味料を使っても料理はなんとか出来上がるのだ。
「確かに既製品のシャツをお召しになる方が圧倒的ですが、一度オーダーシャツをおつくりになったお客さまは、その後は既製品は買われないようです。本当の着心地のよさを知ってしまうからでしょう」
銀座五丁目「ナカヤ」専属のシャツ職人、山本さんは言う。清潔で柔らかそうな襟なしシャツをさり気なく着こなしている。おいしい料理を食べたら後戻りできない。オーダーシャツはそんな感覚と一緒――山本さんの自信みなぎる笑顔はそう語っているようだった。
現代のオーダーシャツづくりは、すべてを一人の職人が行うのではなく、完全分業制を採る。山本さんは「カッター」という中心工程を担う。流れをざっと教えてもらった。
まずは客との商談。
どんなシャツを着たいのか。ナカヤの場合、客の要望を金子章社長がじっくりと聞く。ゆったりと着たい人、ぴったり着たい人、トラッドに着たい人。客にとって当たり前だと思っている嗜好がある。その好みを把握する。このときのコミュニケーションが重要だ。つくり手側が、客の分身のようにシャツづくりに着手できるからだ。たとえば、「オフィスではネクタイを締めるけど、アフター5にはネクタイを外したい」という嗜好ならば、その気分を酌んで襟の部分のつくりを微妙に変える。
次に生地を選んで、採寸。
「肩を少しドロップさせる」、「襟をちょっとだけ高くする」、「少しゆとりをもたせる」など、今度はプロ側の判断を採寸時に加えていく。採寸箇所は多岐に渡り、特に首から肩にかけての角度、肩の厚さを重視する。シャツは、極論すれば肩に乗っかった生地である。だから客それぞれの肩の表情をシャツに反映させなければいけない。
そして山本さんの出番となる。採寸と顧客の綿密な情報が山本さんに渡り、それを元に、自宅の作業場で型紙を起こして生地を切る。型紙起こしには十年はかかると言われている。この、もっとも職人の力量が問われる工程が「カッター」だ。
「採寸表を見て、お客さまの体型を想像して型紙を起こします。採寸とシャツの嗜好を見ると、出来上がったシャツを着ていただいている様子が浮かぶんですね」
このへんが職人の感覚なのだろう。出来上がりを明確にイメージしながら個別の作業に入っていく。
オーダーシャツの生地は既製品には使われていない専用の上物。生地の厚さや柔らかさなどの特徴を山本さんは熟知している。
生地をカットする際、山本さんは裁ち鋏を一切使わない。手にするのは専用の包丁だ。
「鋏は生地を重ねて切っていくと、必ず何ミリかずれが出てしまう。その点、包丁を使うと正確にできます」
包丁は部位別に六種類あり、すべて日本刀と同じ刃だ。昭和三十年の初めにつくったものを使っている。
「数十年使っているんで、研いでいるうちに四割減になってしまいました。毎日、四〜五回研いでいます。包丁なら生地を三十枚重ねてもずれません」
部分的に包丁を使うシャツ職人は多いが、工程のすべてを包丁でこなす職人は数少なくなった。
そして、シャツの各パーツ「前身頃」、「後ろ身頃」、「襟」、「台襟」、「袖」、「胸ポケツト」などを切り終わると、縫いの工程に移り、専門の職人に分散される。縫いが完了したシャツは山本さんに戻る。厳しく上がりを点検して、仕立屋で仕上げをする。そして、再度山本さんに渡り、最終的なチェックを経てナカヤに納品される。シャツは必ず山本さんの目を通過する。「カッター」はシャツづくりの司令塔だ。
出来上がりまでおよそ二週間。オーダーが立て込むのは五月と十月、季節の変わり目が多い。
工程を簡単に追いかけただけだが、「S,M,L」で売られている既製品とは手のかけられ方に雲泥の差があることがわかる。こうして自分だけのためにつくられたシャツが、快適でないわけがない。だから山本さんがつくるシャツには多くのファンがいる。作業場には常連客の型紙が数え切れないほどある。芸能人で懐かしいところを並べると、エノケン、トニー谷、フランキー堺などの面々が得意客だった。ナカヤは元来、ビッグサイズが得意なので、力士のシャツも多く手懸けた。あの小錦(現KONISHIKI)のワイシャツまでつくったほどだ。
山本さんは昭和十一年、愛知県御と津の三河瓦職人の家に生まれた。三人兄弟の次男だった。「言遍に九と上が土下が口」の二字で”やすよし”という難しい名前は、知り合いの僧侶に付けてもらった。自分でも気に入っていると山本さんは笑う。
中学を卒業して、すぐに東京に出た。寄り道せずにワイシャツ職人の道に入った。高校へ進学せず、働きに出るのが当たり前の時代だった。「わたしの主人(師匠の山本惣次さん)の奥様の伯父さんが、たまたま御津の実家の隣に住んでいて、その紹介で東京に来たんです。もちろん、東京への憧れもありました」
辛い修業を覚悟して上京したが、予想に反して穏やかな日々だった。まず、師匠の起こした型紙を切るという作業が与えられた。しかし手取り足取るというわけでもない。洋服には学校があるが、シャツづくりの学校など当時も今もない。職人は白分で技術を身につけ、人に教わることはない。そういう業界だった。
「とにかく見て覚えるしかありません。無口な主人で、二言も口を聞かない日もあったくらいです。手ほどきもされず、怒られもしません。静かな職場でした。しかし主人は元来は厳しい人らしく、戦前はしょっちゅう弟子を竹の物差しでひっぱたいていたそうです。わたしは叩かれたことはなかったんですが」
中学出たてで素直にくるくると働く坊主頭の少年。現在の山本さんの優しげな面差しからすると、少年時代はだれからも好かれる愛らしさだったのだろう。師匠も可愛かったに違いない。
青天の露震がやってくる。山本さんが上京して三年。師匠が脳溢血で急逝した。まだ五十一歳だった。
山本少年は樗然とした。物静かで優しかった師匠の死に直面したのだ。しかし、悲しみに暮れている時間は短かった。
「働き盛りだったせいか、主人は多くの仕事を抱えていました。それをなんとか仕上げなくてはいけない。わたしはまだまだ半人前でしたから、本当に苦労しました。家のほうも、主人はお子さんを戦争で亡くしていたから、奥さん一人になってしまいました」
山本さんは十七歳。その年齢で一家の柱になった。それからは夢中で働いた。休みなど一年に二、三日しかなかった。
高度成長期を経て、いわゆるバブル崩壌を経験した日本。デフレの現状では、値の張るオーダーシャツの需要が減るのも無理はない。なにしろ、既製品には信じられないような安価な値札が付けられているのだ。
「昔は、紳士服は既製品でなくオーダーが当たり前でした。ワイシャツも三十〜四十枚まとめてつくるお客さまも珍しくはありませんでした。一年に百枚もワイシャツをつくる人もいらっしゃったくらいです。高度成長時代から今にかけて、既製品のシャツが主流になってきました。特に今は、着るものが『白由』になってきているんじゃないでしょうか。昔は、芸能人もちゃんとした背広姿でテレビに出ていたけれど、今ではTシャツにジーパンでしょ。そういう影響もあると思うんですね」
確かに、廉価品で育った世代が背広を着るようになれば、オーダーシャツの需要は減る一方だろう。しかしオーダーシャツの着心地のよさ、快適さは厳然たるものがある。味覚と同じでおいしいものはおいしい。
心地よいものはいつの時代でも心地よいはずだ。
「最近のお客さまで三十代の方なんですが、一回つくってとても喜ばれて、それから三十枚以上オーダーをくださった方がいるんです。着ていてとても気分がよいとおっしゃるんです。着心地を気に入って、二枚目をつくりに来てくださるときがいちばんうれしいですね。ウチのシャツは首と肩のバランスを綴密につくりますので、着心地がとても白然との評価をいただいています。肩のサイズが合わないシャツは、着ているだけで肩が凝ったりするんです。五十代のお客さまから、おたくでシャツをつくってから、不思議と肩凝りがなくなったと言われたこともあるんですよ」
山本さんの表情に誇らしげな色が宿っている。
ナカヤのオーダーシャツは一枚一万六千円〜二万一千円(ヨーロッパ製生地・二万円〜二万八千円)。
海外のブランドシャツなどと比べても値段に差がない。ならば、自分のためだけにつくられたシャツを着たいと思う。職人の技を満喫でき、体の不調まで改善するかもしれず、そして四六時中、極上の気分を堪能することができるのだ。
「銀座百点」平成13年9月号より
文 須藤 靖貴